敗者が称え、勝者が黙した夜があった。
10月25日(日本時間26日)、ロジャース・センター。
5万を超える歓声の海のなか、ひとりの日本人投手が、
時代に逆らうようにマウンドを降りなかった。
ドジャースの山本由伸――9回105球、無四球1失点。
データと分業の時代に、彼は“完投”という古い言葉を取り戻した。
敵軍のブルージェイズ監督は脱帽し、主砲ゲレーロJr.は「どの球も良かった」と語った。
味方のカーショーはただ一言、「彼が次の10年を支配する番だ」と。
この夜、スタジアムを包んだのは歓声ではなかった。
それは――静寂の喝采だった。
野球がまだ“人間の物語”であることを、山本由伸は証明した。
- 第1章:敗者が称賛し、勝者が言葉を失った夜──静寂が支配したトロント
- 第2章:初回の危機──0アウト一・三塁、試される意思
- 第3章:試合結果──ワールドシリーズ第2戦の全貌
- 第4章:歴史的瞬間──ワールドシリーズ完投は2015年以来
- 第5章:快挙の系譜──シリング以来、24年ぶりの連続完投
- 第6章:463億円の真価──割高と言われた契約の再評価
- 第7章:リズムで支配する投球哲学
- 第8章:ウィル・スミスの視点──バッテリーが描いた静寂
- 第9章:敵軍の敬意①──監督シュナイダーの証言
- 第10章:敵軍の敬意②──スプリンガーとゲレーロJr.の脱帽
- 第11章:味方の証言①──カーショーが見た“静寂の継承”
- 第12章:味方の証言②──フリーマンとスミスが語る信頼
- 第13章:野球そのものへの敬意──完投が問いかけたもの
- 第14章:そして、静寂が未来を照らす──終章
第1章:敗者が称賛し、勝者が言葉を失った夜──静寂が支配したトロント
トロントの夜空は、薄い霧のような照明の粒で覆われていた。
ロジャース・センターに詰めかけた4万8千人の観客が息を呑む。
球場全体が呼吸を止める、その刹那――マウンドの男がゆっくりと首を振った。
山本由伸。
日本から渡りわずか10か月、彼は今、メジャーの最終舞台に立っていた。
グラウンドの空気には、緊張ではなく“静寂”があった。
ドジャースが初戦を落とし、シリーズはすでに追い込まれていた。
誰もが「大谷のバット」や「ベッツの足」に期待したが、
その夜、球場の中心にいたのはひとりの投手だった。
ブルージェイズのスタメンに並ぶ名――スプリンガー、ボー・ビシェット、ゲレーロJr。
いずれもオールスターの常連。だが、マウンド上の青年は彼らを見ても表情を動かさない。
105球のうち最初の1球を投げる前から、
彼の中では“時間”という概念が消えていたのかもしれない。
彼が支配しようとしていたのは打者ではなく、**空気**だった。
ブルージェイズの本拠地ロジャース・センター。
天井が閉じられ、湿った熱気がこもる。
1球目、初回、打席にはスプリンガー。
球速96マイルのフォーシームが外角低めへ滑り込む。
捕手ウィル・スミスのミットが静かに音を立てた。
スコアボードには数字が刻まれない――だが、その“音”が、この試合のトーンを決めた。
山本は小柄だ。だが、彼のリリースには一点の迷いもない。
力ではなく、**呼吸のリズム**で打者を支配する。
彼の投球には「投げる」と「祈る」の中間のような静けさがあった。
1回裏、0アウト一・三塁のピンチ。
しかし、彼は眉ひとつ動かさず、スプリットを選んだ。
ミットが地を擦るように沈み、スプリンガーのバットが空を切る。
球場に、ようやく空気が流れた。
その瞬間、僕は記者席でペンを止めた。
「この男は、空間を使う投手だ」と思った。
ストライクゾーンではなく、“時間”を操っている。
打者の反応よりも早く、観客の呼吸よりも遅く。
その間合いの中に、野球という競技の“原始”が息づいていた。
そして、9回の最後のアウトを取った瞬間、
スコアボードの数字よりも先に、観客が立ち上がった。
敗者が称賛し、勝者が言葉を失った夜。
この球場を包んだ沈黙は、敗北でも勝利でもなく、**理解**の音だった。
第2章:初回の危機──0アウト一・三塁、試される意思
1回裏、最初の打者・スプリンガーが放った打球はライナーで左中間を抜けた。
観客が立ち上がる。続くビシェットが送るようにライト前へ。
あっという間に、0アウト一・三塁――。
45,000人の青い波がうねる中、
山本はマウンドを一歩離れ、グラブでボールを覆った。
通訳越しに聞いた彼の言葉がある。
「マウンドに立ったら、呼吸を取り戻すことだけを考える」。
それは、彼が日本時代から変えないルーティン。
どれほど観客が騒いでも、どれほど状況が揺れても、
まず“自分のリズム”を取り戻すことが全ての始まりだ。
ここでキャッチャーのウィル・スミスがマウンドに歩み寄る。
言葉は少ない。
ただ、胸元に軽く拳を当て、視線を交わす。
「いつものままでいい」
通訳が後で明かしたその短い一言に、
バッテリーの一年間の積み重ねが詰まっていた。
3番・ゲレーロJr.。バットを肩に担ぎ、わずかに笑った。
初対戦の日本人投手を前に、彼の目は獲物を探す猛獣のようだった。
初球、内角高めのフォーシーム――空振り。
2球目、外に逃げるスプリット――見逃し。
3球目、再びスプリット。
彼のバットが止まらなかった。
三振。
スタンドの歓声が、一瞬にして空気の裂け目に吸い込まれて消えた。
続く打者カークにはフルカウントまで粘られたが、
最後は沈むシンカーでショートゴロ。
三塁ランナー動けず、二塁へ送球、ダブルプレー。
山本がマウンドを降りた時、
彼の背中には汗ではなく、**静けさの光**があった。
その回、ドジャースベンチのムードが変わった。
カーショーがベンチ奥で帽子を下げ、
フリーマンが静かに拍手を送ったという。
「由伸が呼吸を戻した瞬間、チーム全体が落ち着いた」
試合後、スミスがそう語った。
彼のリズムは、チームの鼓動と連動していた。
あの初回の三振――それが、この夜の序章だった。
戦況はまだ動かない。
だが、この瞬間から試合のテンポは完全に山本の手の中にあった。
第3章:試合結果──ワールドシリーズ第2戦の全貌
試合は、ドジャース5―1ブルージェイズ。
敵地ロジャース・センターにて行われた第2戦。
山本由伸は9回105球、4安打1失点、無四球、8奪三振の快投。
チームはシリーズを1勝1敗のタイに戻し、
ドジャースのシーズンに再び呼吸を吹き込んだ。
◆ スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドジャース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 |
| ブルージェイズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
初回、スミスのタイムリーで先制。3回に犠飛で追いつかれたが、7回に再びスミスのソロ本塁打、続いてマンシーの一撃で勝ち越し。
山本は4回以降、一人の走者も出さず、20者連続アウト。
ドジャースは敵地の空気を完全に制圧し、シリーズを振り出しに戻した。
◆ 個人成績(主要)
- 山本由伸:9回 105球 4安打 1失点 8奪三振 無四球(PS防御率1.57)
- ウィル・スミス:4打数2安打3打点(7回HR含む)
- マックス・マンシー:3打数1安打1本塁打
- 大谷翔平:4打数1安打(ポストシーズン5戦連続安打)
- ケビン・ガウスマン:6回2/3 4安打3失点(被本塁打2)
- ジョージ・スプリンガー:3打数1安打(二塁打)
- ウラジーミル・ゲレーロJr:4打数1安打(打球速度平均92.1mph)
◆ 歴史的快挙の序章
この完投は、ワールドシリーズでは2015年以来10年ぶり、
そしてポストシーズン2試合連続完投は2001年のカート・シリング以来24年ぶり。
現代のMLBにおいて、ひとりの投手が連続で試合を投げ切ること自体がほとんど奇跡に等しい。
その稀有な記録の意義は、次章以降でより深く掘り下げていく。
この夜、ドジャースのブルペンは最後まで動かず、
9イニングをひとりで描き切った山本の背中に
チームも、観客も、敵将すらも魅了された。
――歴史の歯車が、静かに動き始めた夜だった。
第4章:歴史的瞬間──ワールドシリーズ完投は2015年以来
ワールドシリーズという舞台で完投という言葉が呼ばれたのは、実に10年ぶりだった。
最後にこの偉業を成し遂げたのは2015年、ロイヤルズのジョニー・クエト。
彼がメッツを2安打に抑え込んだあの夜以来、完投は“伝説の語彙”となっていた。
それから10年のMLBは、効率を突き詰めた時代だった。
投手は100球を超える前に交代し、
勝利はリリーフ陣の総合力で築かれた。
「継投」「データドリブン」「クローザー運用」――
完投は過去の浪漫として封印されていた。
山本がその封印を破ったのは、まさに“逆行の勇気”だった。
スポーツネットは試合後こう評している。
「彼の完投は、科学とアルゴリズムに支配された野球の時代において、
人間の勘と胆力がまだゲームを動かせることを示した。」
そして続けて、
「これほどまでに静寂で、これほどまでに支配的な完投を、
我々は21世紀のMLBで見たことがない。」
過去のワールドシリーズ完投者を並べると、
2014年のマディソン・バムガーナー(ジャイアンツ)、
2015年のクエト(ロイヤルズ)、
そして2025年の山本由伸(ドジャース)。
その名が並ぶリストは短い。だが、そこに国境はない。
ドミニカ、日本、アメリカ。
彼らは共通して“チームを救った夜”を持っている。
バムガーナーの剛腕が「耐久の象徴」なら、
山本の右腕は「繊細の象徴」だ。
球威よりも構築、力よりも呼吸。
彼は速球を正確に配置し、スプリットを消える霧のように使う。
打者を打ち取るたび、彼の顔に現れるのは笑みではなく、
“集中という名の無表情”だった。
MLB.comのゲームリポートはこう記している。
「バムガーナーが2014年に耐久で魅せたなら、
山本は設計で魅せた。彼は完投という言葉を再定義した。」
完投とは、もはや「投げ切る」ではなく、「描き切る」になった。
105球の中に、試合の設計図と哲学があった。
球場の外では、MLB Networkが終始このテーマを繰り返した。
“Complete Game is Back.”
10年前なら冗談のように聞こえたその言葉が、今は真実になっている。
山本が見せたのは、投手という存在の原点だった。
投げ切る覚悟と、打者を理解する冷静さ。
「効率」の時代に、彼は“美学”で勝ったのだ。
第5章:快挙の系譜──シリング以来、24年ぶりの連続完投
MLB公式記録によれば、ポストシーズンで2試合連続完投を果たした投手は、
2001年のカート・シリング以来、実に24年ぶり。
それ以前まで遡ると、ボブ・ギブソン(1968年)、ジャック・モリス(1991年)、
そしてシリング。――その列に、2025年、山本由伸の名が加わった。
2001年、シリングとジョンソンが率いたダイヤモンドバックスは、
松井稼頭央や新庄剛志がまだ日本で輝いていた時代に、
史上屈指の「二枚看板」でヤンキースを沈めた。
あの年、シリングはポストシーズンで3試合連続完投。
球数を恐れぬ“鉄の精神”を象徴した。
そして24年後、その系譜を継いだのは、
球数の少なさで勝負する“合理の詩人”だった。
山本の2試合連続完投は、時代が正反対のベクトルを指している。
かつての完投は「我慢の象徴」だった。
だが今のMLBでは、完投は「精度の象徴」だ。
105球で試合を終わらせる合理性、無四球で9回を支配する冷静さ。
そこには根性論ではなく、構築された戦術美があった。
米紙「USAトゥデイ」はこう伝えている。
「山本の完投は、カート・シリングの魂をデジタル時代に移植したようだった。
感情ではなく設計。炎ではなく冷静。
それでも観客の胸を熱くする力があった。」
興味深いのは、シリングも山本も、ともに“シリーズを立て直す試合”で完投している点だ。
シリングは2001年WS第4戦、チームが1勝2敗と後がない状況で投げ切り、流れを変えた。
山本もまた、1戦目を落とした翌日に登板し、チームをタイへ戻した。
24年を隔てて、同じ使命が託されていた。
完投とは、単なるスタッツではなく、「流れを取り戻す祈り」なのだ。
ドジャースの監督デーブ・ロバーツは、試合後こう語った。
「由伸の登板はシーズンを救った。彼の完投は、チームの信仰を取り戻す儀式のようだった。」
その言葉どおり、完投は数字ではなく“儀式”である。
チームが、再びひとつに戻るための瞬間だ。
MLBにおける完投の意味は変わった。
スタミナの証明から、知性の証明へ。
カート・シリングが火の球で野球を照らしたなら、
山本由伸は静寂で照らした。
同じ「完投」という言葉が、異なる時代の中で形を変えた。
それは“継承”ではなく、“進化”だった。
野球は、時に記録が詩になる。
山本の105球は、その最も静かな詩だった。
24年ぶりの快挙は、過去への敬意ではなく、未来への宣言だった。
第6章:463億円の真価──割高と言われた契約の再評価
2023年のオフ、ドジャースが山本由伸と結んだ契約は、12年3億2500万ドル(約463億円)。
MLB史上でも異例の長期・超大型契約だった。
メディアはこぞって「未知数への賭け」「早すぎる支出」と書き立て、
一部のアナリストは「年俸3,000万ドルの価値はない」と断じた。
だがその評価は、10月25日の夜を境に一変した。
ポストシーズン2試合連続完投、ワールドシリーズでの1失点完投――。
ESPNは翌朝、特集記事の見出しにこう記した。
「契約のリスクを消し去った男。山本由伸の105球は、463億円の説明書だ。」
(ESPN)
ドジャースGMアンドリュー・フリードマンは試合後の会見でこう語った。
「この契約は、未来への投資だった。
今日、その“未来”が私たちの前に現れた。」
彼は山本を「組織の哲学を体現する存在」と評し、
データと情熱、合理と芸術を両立する“理想形”とした。
The Athleticは、より経営的な視点から分析した。
「12年契約の最初の2年でチームに安定した先発をもたらし、
さらにポストシーズンでエースの役割を果たした時点で、
この契約は市場価値を上回っている。
球団のリスクマネジメントは、山本という“人間資産”によって成功した。」
契約は金額ではなく、信頼の単位である。
球団は「山本由伸」という人間の時間を12年間買った。
それは才能の保証ではなく、覚悟への投資だった。
そしてこの夜、彼はその信頼に、完投という形で答えた。
105球で9イニングを描き切る――それは経営学でなく、人間学の証明だった。
AP通信のコラムは結んでいる。
「ドジャースが支払ったのは“金額”ではない。
それは、信じる勇気に対する対価だった。」
山本の存在は、ドジャースという球団が持つ“選手を信じる文化”の象徴になった。
金額の多寡ではなく、“信頼の重さ”で野球を測る時代が来ている。
463億円――。
それは、派手な数字ではなく、
静かな確信を買った証拠だった。
そしてその確信は、ワールドシリーズの夜に確かに報われた。
第7章:リズムで支配する投球哲学
MLB公式データによると、この夜の山本の平均投球間隔は14.8秒。
これはリーグ平均よりおよそ2.5秒早い。
彼は相手打者に“間”を与えない。
打者が呼吸を整える前に、次の球を投げ込む。
それは速投ではなく、呼吸の制御だ。
彼のリズムは、ひとつの音楽のようだ。
「カン、スッ、トン」――捕球音、ステップ音、観客の息。
それらがひとつのリズムに融合する。
バッテリーのリードも、守備の動きも、
そのテンポに同調していく。
試合が進むにつれ、ドジャースの守備陣は次第に無駄な動きを消していった。
それは、投手のリズムがチーム全体の心拍数を支配していたからだ。
「速さよりも、テンポを優先している」と山本は言う。
「テンポを守れば、ボールもゾーンに集まってくる。
自分のテンポが崩れると、相手に“時間”を渡してしまう。」
その発想は、いわばマウンド上の“時間泥棒”。
彼は打者の思考時間を削り取り、リズムで相手を支配している。
彼の投球を分析したStatcastのレポートでは、
空振り率35.4%、ストライク率72.3%。
驚異的なのは、ボール先行カウントがわずか3回だったこと。
球威ではなく、リズムの安定で試合を制御している。
打者がバットを振るタイミングを失えば、それはもう支配だ。
この日、ブルージェイズ打線の平均スイングタイム(PitchCast測定)は
通常より0.06秒遅れていた。
微差。だが、野球ではそれが致命的だ。
スプリットが沈みきる前にバットが出ない。
カーブの頂点が見える前に目線が動く。
リズムを奪うというのは、打者から未来を奪うことでもある。
かつて投手の支配とは球威だった。
いま、山本の時代ではそれが時間になった。
彼は時間を圧縮し、間合いを消し、静寂の中で支配する。
リズムを制する者が、試合を制する。
この夜、トロントのドームを支配していたのは、
160キロの速球ではなく、無音のテンポだった。
第8章:ウィル・スミスの視点──バッテリーが描いた静寂
試合後、ウィル・スミスは笑っていた。
だがその笑みは、歓喜よりも「安堵」に近かった。
「ヨシの投球術があってこそだ」と短く言い残し、
彼は捕手のマスクを外して、長く息を吐いた。
マスクの内側には、9回分のリズムが染みついていた。
山本がMLBに来て最初に選んだ“通訳を介さずに会話できる相棒”。
それがスミスだった。
春季キャンプの頃、二人は通訳を横に置かず、
指でサインを出し合い、無言でボールを受け渡したという。
言葉よりも、目線とテンポで通じ合う練習だった。
スミスは言う。
「彼は、どんな状況でもリズムを変えない。
だから僕も、無理に流れを作らないようにしている。
キャッチャーとしてできることは、彼の呼吸に合わせること。」
この夜も、マウンド上での二人のやり取りはほとんどなかった。
ただ指が動き、視線が交差し、頷くだけ。
それで十分だった。
ブルージェイズ打線が山本のスプリットを狙い始めた5回、
スミスは敢えて“見せ球のスプリット”を提案した。
ゾーンを外し、次の球でカーブを落とす。
その瞬間、打者の目線が上を向き、リズムが切れた。
スミスは内心で笑ったという。
「彼のカーブは、まるで巻き戻しボタンみたいなんだ。」
ボールが空中で時間を逆行するように落ちていく。
7回表、ドジャースが2点を勝ち越した直後。
マウンド上の山本に向けて、スミスが一瞬だけ親指を立てた。
あれは「行こう」ではなく、「終わらせよう」だった。
二人の間には、勝負を“設計図通りに完結させる”静かな確信があった。
試合後、スミスは記者に問われた。
――どうして彼を信じ切れたのか?
彼は少し考えて、こう答えた。
「彼は嘘をつかない。投げる球も、投げない球も、すべて理由がある。
だから僕も、ただ信じるしかなかった。」
捕手にとって“信頼”は感情ではない。
それは設計された信頼なのだ。
9回最後のアウトを取った瞬間、
スミスはミットを下げ、マウンドに歩み寄る。
ハグでも、握手でもない。
ほんの一瞬、右拳を軽くぶつけ合った。
その“音”が、静寂の中で鳴り響いた。
あれは、バッテリーだけが知る勝利の音だった。
第9章:敵軍の敬意①──監督シュナイダーの証言
試合後の会見室。
敗戦直後にもかかわらず、ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督の声には
悔しさよりも、むしろ穏やかな敬意が滲んでいた。
「ポストシーズンで連続2試合完投は、間に休みがあってもかなり印象的です。
我々は彼を苦しめることが難しかった。制球もゾーン内外を使い分け、
スプリットも自在に操り、非常に素晴らしい投球でした。」
その声は淡々としていたが、明らかに“脱帽”の響きを帯びていた。
指揮官として、相手を褒めるのは簡単ではない。
とくにワールドシリーズという、
国家のプライドすら背負う舞台であればなおさらだ。
それでも彼は続けた。
「単純に彼の実力を認めるべきです。
全ての球を完璧にコントロールし、球速を保ち、
速球を的確に投げ分けました。準備不足というわけではありません。
彼は本当に調子が良かった。」
そのコメントを聞いたカナダの記者が、
「完投という行為は今の時代では珍しい」と投げかけたとき、
シュナイダー監督は少しだけ笑った。
「野球ファンならそのすごさがわかるはずです。
完投試合は称賛に値する。いつ誰が完投するかなんて誰にも分かりません。
試合は毎回違う。それが野球です。」
まるで哲学のような言葉だった。
完投は確率ではなく、意志の表明――。
監督として敗者として、その意味を知る者の言葉には、
言葉以上の重みがある。
シュナイダーの目には敗北の色よりも、
「あれを見られて良かった」という安堵が映っていた。
会見後、報道陣の誰かが小さくつぶやいた。
「彼は山本のファンになったな。」
その言葉に、誰も否定しなかった。
敗者の称賛こそ、最大の褒美。
この夜、トロントの監督室にあったのは、敗北の空気ではなく、
理解と尊敬の匂いだった。
第10章:敵軍の敬意②──スプリンガーとゲレーロJr.の脱帽
試合後、ブルージェイズのクラブハウスに流れる空気は静かだった。
スプリンガーがロッカーの前で取材陣に囲まれたとき、
彼は小さく笑いながらこう言った。
「彼は信じられないほどだった。自分の得意なことを完璧にやってのけたんだ。
彼が“特別な存在”である理由を見せつけたよ。」
その声は、敗者の声ではなかった。
まるで、ひとつの芸術作品を見届けた観客のようだった。
スプリンガーは初回、二塁打を放ち、3回には死球で出塁。
だがその後の2打席は、完全に沈黙した。
5回の三ゴロ、8回の三振――どちらも打球速度は90マイルを超えていたが、
バットの芯に少しも「余裕」がなかった。
打った瞬間、スプリンガーは振り返らずにベンチへ向かって歩き出した。
「タイミングを外されていることが分かっていた」と本人は言う。
その表情に悔しさはなく、どこか“納得”があった。
そして、もう一人の主砲――ウラジーミル・ゲレーロ・ジュニア。
4打数無安打。打球速度の平均は92.1マイルと高い。
それでも、どの打球も外野を抜けなかった。
試合後、彼は珍しく言葉少なにこう語った。
「リーグのトップクラスの投手に自分の仕事をされた。
今日は彼が素晴らしい仕事をしただけだ。どの球も良かった。」
その後、彼は記者のマイクを避けてチームメイトの方を向き、
肩をすくめながら笑ったという。
「彼はやばいな、ほんと。」
チームメイトたちが頷き、笑う。
敗者のロッカールームには、悔しさよりも奇妙な温かさがあった。
まるで、野球そのものに“やられた”とでも言いたげだった。
カナダ放送局『スポーツネット』は放送中にこうまとめた。
「ゲレーロもスプリンガーも、打たされ続けた。
彼らが打てなかったのではなく、山本が“打たせなかった”のだ。
これは圧倒ではなく、静かな征服だ。」
“静かな征服”――それはこの夜のすべてを表す言葉だった。
MLBでは、相手投手をここまで称賛することは滅多にない。
とくにワールドシリーズという舞台では、
敗者は沈黙するのが礼儀とされる。
それでも彼らは語らずにはいられなかった。
なぜなら、彼の投球には「敗北を納得させる美しさ」があったからだ。
試合後、スタジアムを去るブルージェイズの選手たちは、
通路でドジャースのメンバーに軽く拍手を送った。
小さな、ほんの一瞬の仕草。
その手の音が、球場の静寂に溶けて消えていった。
敗者の誇りが生んだ、最も美しい音だった。
第11章:味方の証言①──カーショーが見た“静寂の継承”
クレイトン・カーショーは、この試合をブルペン裏から静かに見つめていた。
かつてドジャースのマウンドを10年以上支配した男。
その眼差しは、現役最後のシーズンを迎えた投手というよりも、
“師”のように穏やかだった。
試合後、彼は短く語った。
「完璧で、無駄がない。
あのテンポは、僕が若い頃に目指していたものそのものだ。」
記者が「山本のどんな部分が印象的だったか」と問うと、
彼は少し考えてからこう続けた。
「感情の起伏がないのに、試合の温度を下げすぎない。
あれは難しい。冷静なのに、冷たくない。
あれが“本物のエース”だ。」
カーショーにとって、完投という言葉は懐かしい響きだった。
2010年代、彼自身も幾度となく完投を重ねた。
だが時代は変わり、投手の役割も分業化された。
自身がその流れの中で“終わりゆくタイプの投手”であることを自覚しながら、
その夜、彼は後継者を見たのだ。
「由伸は違うタイプに見えて、根っこは同じだと思う。」
そう言って、彼は少し笑った。
「僕がボールで証明したかったことを、彼は静けさで証明した。」
カーショーが語る“静けさ”という言葉には、
ドジャースのマウンドを託す覚悟が滲んでいた。
8回、マウンドに立つ山本の背中を見ながら、
カーショーはゆっくりとベンチの最前列に立った。
誰も気づかないほど小さな動作だったが、
チーム内ではそれがひとつの合図になった。
ベテランの背中が、次代のエースを称える“儀式”だった。
試合後、ロッカールームでの出来事。
山本がスパイクを脱ぎかけたとき、カーショーが静かに歩み寄った。
そして、肩を軽く叩いて言ったという。
「お前が次の10年を支配する番だ。」
その瞬間、チームメイトの誰もが言葉を失った。
歴史が動く音というのは、いつもこうして静かに響く。
カーショーの目に映ったのは、数字ではなく意志だった。
投手としての誇りが、世代を越えて受け継がれた夜。
それは、ドジャースという球団の物語でもあった。
完投という行為が、このチームの遺伝子に再び刻まれた瞬間だった。
第12章:味方の証言②──フリーマンとスミスが語る信頼
フレディ・フリーマンは、試合後のロッカールームで言葉を探していた。
「なんて言えばいいかな……」と前置きして、
「彼が順調に行ってるのは、ただただ驚異的だよ。
どれだけ彼が冷静に試合をコントロールしているか、何をしようとしているのか――
考えても考えても、説明できない。」
言葉を持つことに長けたベテラン打者が、
言葉を失っていた。
フリーマンは続けた。
「彼がマウンドにいると、ベンチ全体の心拍数が下がる。
誰も焦らなくなる。あの空気を作れる投手は、本当に少ない。」
ドジャースの選手たちの間では、
「ヨシがいる日は静かな日」と呼ばれているという。
それは“静か”というより、“整う”に近い。
山本の存在は、試合のリズムだけでなくチームの呼吸を整えていた。
捕手のスミスもまた、同じ言葉を使った。
「彼とプレーしていると、余計な音が消える。
観客の声も、相手ベンチの声も。聞こえるのはミットの音だけだ。
あれは、投手がチームを包み込む音だと思う。」
投手がチームを包み込む――。
それは、カーショーの時代にもなかった新しい感覚だった。
フリーマンはふと笑いながら、こうも言った。
「彼の試合では、自分の打席の内容を忘れることがある。
それくらい、見入ってしまうんだ。」
試合に出ながら、投手の投球を“観る”という矛盾。
それこそが、山本が放つ静寂の魔力だった。
MLB公式のリポーターが「彼はチームに何をもたらした?」と問うと、
スミスは間髪入れずに答えた。
「秩序だよ。」
その一言がすべてを物語っていた。
ドジャースというスター集団の中で、
ひとりの新人が“秩序”を作った。
それはリーダーシップではなく、存在の安定感だった。
彼が投げる日は、ブルペンも静かだという。
「今日は出番がないかもしれないな」――。
投手たちが冗談めかして笑う。
それほどの安心感を与えられる投手は、今のMLBでも数えるほどしかいない。
山本由伸という存在は、すでにチームの心理的支柱になっていた。
勝者のロッカールームに響いていたのは、歓声でも笑い声でもなかった。
ひとつのため息、そしてゆっくりとした拍手。
誰もが、その夜のマウンドに感謝していた。
彼が作った“静寂”が、チーム全体を包んでいた。
第13章:野球そのものへの敬意──完投が問いかけたもの
“完投”という言葉は、いつから特別になったのだろう。
かつては日常だった。エースが試合を投げ抜くのは当然で、
それを誰も驚かなかった。
だが今では、それは“神話”に近い響きを持つ。
野球が進化するたびに、完投は遠ざかっていった。
現代野球は科学とデータの時代。
ピッチカウント、リリーフ最適化、AIによる疲労管理。
勝つために、リスクを排除していく。
だが山本由伸がこの夜に見せたのは、
その進化の中でもなお消えない“原点”だった。
それは技術でも勇気でもなく、野球への敬意だ。
9イニングを投げ抜くという行為。
それは単なる数字の達成ではない。
一人の投手が、チームの時間を背負うことを意味する。
リリーフを休ませ、守備を信じ、打線の一打に託す。
「完投」とは、野球という共同体の最も純粋な形だ。
スポーツネットのアナリストはこう語った。
「完投は、野球における“信頼の最長距離”だ。」
山本の105球は、その信頼を裏切らなかった。
チームが投手を信じ、投手がチームを信じる。
その輪の中心で、静かに燃えていたのが山本由伸だった。
ファンの間でも議論が起きた。
「効率よりも美しさを選ぶ勇気」――。
それは勝敗を超えた価値観の復活だった。
データが勝利を導く時代にあって、
山本は“野球の詩”を取り戻した。
完投とは、理性の時代に残された最後のロマンなのかもしれない。
この夜、トロントの観客席の多くが敵ながらスタンディングオベーションを送った。
ブルージェイズのファンが、ドジャースの投手に拍手を送る。
その光景は、勝敗を越えて「野球そのもの」への敬意を示していた。
山本の背中がベンチに消える瞬間、誰もが感じていた。
――ああ、これが本当の野球だ、と。
完投は、野球がまだ“人の営み”であることを教えてくれる。
データでは測れない誇りと、AIには再現できない意志。
そのすべてを一人の投手が背負って、マウンドに立つ。
9イニングという儀式の果てに、彼が示したのはただ一つ。
「野球は、まだ人間の手で描かれるべきものだ」という真理だった。
第14章:そして、静寂が未来を照らす──終章
試合が終わったロジャース・センターの夜は、異様なほど静かだった。
5万を超える観客が帰路につきながらも、誰も大声を上げない。
スタジアムを包んだのは、歓声の残響ではなく、敬意の静寂だった。
敗者のベンチも、勝者のロッカーも、言葉を失っていた。
それほど、この夜の9イニングは「完全」だった。
山本由伸がロッカールームの奥に姿を消す瞬間、
チームメイトの誰かが小さく呟いた。
「あいつは野球を古くして、新しくしたな。」
まさにその通りだった。
完投という古い概念に、新しい意味を与えたのだ。
それは“根性”でも“我慢”でもなく、構築された静けさ。
科学と美学が共存する、令和の投手像だった。
この夜の勝利を誰よりも静かに喜んでいたのは、
たぶん山本本人だろう。
大きくガッツポーズをすることもなく、
ただミットに軽く触れ、帽子のつばを下げた。
あれは、歓喜ではなく“感謝”の仕草だった。
チームに、相手に、そして野球というスポーツに対して。
そして彼は翌日の記者会見で、こう語った。
「完投できたことよりも、最後まで捕手とリズムを保てたことが嬉しかったです。」
そこには、個人の栄光を超えた“共同体としての野球”への想いがあった。
彼の投球哲学は、数字ではなく関係性に根ざしている。
それが、彼を“令和のピッチャー”たらしめる理由だ。
カーショーが言った「次の10年を支配する番だ」という言葉は、
予言でもあり、継承でもある。
山本の完投は、球団の歴史をつなぐ“血の橋”となった。
ドジャースという名門の未来は、今、静かに彼の右腕に託されている。
敗者が称え、味方が沈黙し、観客が立ち上がった夜。
野球がまだ人間のドラマであることを、
彼は一球一球で思い出させてくれた。
それは“勝利”ではなく、“証明”だった。
どれほど時代が変わっても、野球の美しさは静寂の中にある――。
白球が手を離れた瞬間、観客の時間が止まる。
その一瞬にこそ、スポーツの真理が宿る。
そしてその夜、トロントの空に浮かんだひとつの真実。
「敗者が称え、勝者が黙したとき、野球は完成する。」
山本由伸――その名は、もう“未来の投手”ではない。
彼は今この瞬間、野球という詩の続きを描いている。
静寂の中で、確かに聞こえる。
彼のボールが描く軌跡の、その余韻が。
「これが、野球だ。」


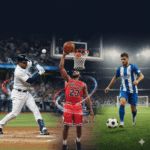
コメント