ワールドシリーズは2勝2敗のタイで迎えた第5戦を、ブルージェイズが6−1で制して対戦成績を3勝2敗とし、32年ぶり3度目の世界一に王手をかけた。ドジャースは本拠地で連敗。舞台はトロントへ移り、日本時間11月1日の第6戦は山本由伸が先発する。ここでは第5戦から読み取れる技術的・戦術的示唆を抽出し、第6戦の見どころを中立的視点で整理する。
- 第5戦スコアと先発・本塁打
- 初回3球で2失点――「ゲームの重心」が即座に移った理由
- 唯一の反撃はK・ヘルナンデスのソロ――“ムード”は変えたがスコアは動かせず
- イェサベージ(22)が「新人の壁」を粉砕――7回1失点12K無四球の理由
- 大谷翔平:4の0も“打球質”は改善の兆し(中立評価)
- “7回の壁”が連続で露呈――継投と守備のミクロ精度
- ベッツの不振とロバーツの信頼――「中心は中心であり続ける」
- 第6戦:山本由伸は“序盤3イニング”で試合の温度を下げられるか
- 第6戦の勝敗を分ける「3つの分岐点」
- 確率の現実と“反発力”――25.9%は低いか、高いか
- 守備・捕手の視点――“1球の価値”を最大化する
- 攻撃の再設計――「ボール1つ下」の見極めと、球数の作り方
- 結論:必要なのは“完璧”ではなく“反発”――第6戦のキーワード
第5戦スコアと先発・本塁打
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルージェイズ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| ドジャース | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【ド】スネル ― エンリケス ― バンダ ― トライネン / 【ブ】イェサベージ ― ドミンゲス ― ホフマン
【本】シュナイダー1号、ゲレーロJr.8号(ブ)、K.ヘルナンデス1号(ド)
初回3球で2失点――「ゲームの重心」が即座に移った理由
先発ブレーク・スネルは、先頭デービス・シュナイダーに初球先頭打者弾、続くウラジーミール・ゲレーロJr.にも2球目ソロを被弾。ワールドシリーズで先頭からの二者連続本塁打は史上初であり、開始わずか3球で2失点という異例の立ち上がりとなった。ブルージェイズは「最初のスイングから仕留める」事前アプローチを貫徹。高めゾーンの4シーム/チェンジ・オブ・ペースの見せ球を、狙い撃ちのフルスイングで切り裂いた。ここで主導権・心理・スタジアムの空気が一気にアウェイ化し、ドジャースは以降の攻守で常に「追う側」のテンポを強いられた。
唯一の反撃はK・ヘルナンデスのソロ――“ムード”は変えたがスコアは動かせず
3回裏、キケ・ヘルナンデスがレフトへソロ弾。逆方向寄りの球に対するバットコントロールの巧さが光り、スタンドの空気も一時的に反転した。しかし、再現性のあるチャンス構築(出塁→進塁→適時打)にはつながらず、結果的にこの1点が唯一の得点。以降は走者を塁上に置いても、追い込まれたカウントからの空振り/凡打が続き、得点期待値(チェインの起点)が伸びない展開だった。
イェサベージ(22)が「新人の壁」を粉砕――7回1失点12K無四球の理由
ブルージェイズのトレイ・イェサベージは、7回104球・1失点・12奪三振・無四球・被安打3。WS新人の1試合最多奪三振を更新し、22歳以下の12Kは113年ぶりという歴史的快投となった。第1戦と比べ、スプリット×スライダーの配球比率と投球質が明確に向上。スプリットは4シームと同トンネルから「テーブル落ち」する軌道で、空振り・ゴロの双方を量産。スライダーは左打者の膝元・右打者の外へ出し入れ幅を増やし、見逃しと空振りの両取りを実現した。
会見での「ただの三振だ」という冷静な言葉どおり、ゾーンの上下幅と初球ストライク率が序盤から機能。無四球は、カウント不利を自ら作らなかった証左である。
大谷翔平:4の0も“打球質”は改善の兆し(中立評価)
大谷は4打数無安打(WS2試合連続ノーヒット)。ただし、内容評価は一枚岩ではない。第3打席では打球速度117.3mph(約189km/h)の弾丸ライナーを右翼へ放ち、バージャーのスーパーダイブに阻まれた。これはStatcast換算で高い安打期待帯の打球質であり、「当たりの質」は明確に上がっている。他の打席は、外角低めスプリットの見極めミス(第2打席)や、真ん中スプリットの芯外し(第4打席)があり、投手の球質と配球に軍配が上がった面は否定できない。
結論:結果が出ていないのは事実だが、復調の初期シグナル(打球速度・球筋への適応)は確認できる。第6戦での「最初の1本」が、打線全体の圧を押し返す触媒になりうる。
大谷の打席ログ(第5戦)
- 第1打席:投ゴロ(外角直球153.6km/h、高バウンド)
- 第2打席:空振り三振(外低スプリット136.5km/h)
- 第3打席:右ライナー(117.3mph、ダイビングキャッチ)
- 第4打席:一ゴロ(真ん中スプリット139km/h)
“7回の壁”が連続で露呈――継投と守備のミクロ精度
第4戦・第5戦ともに7回に失点。第5戦はスネルの暴投2つ、継投したエンリケスの暴投で走者進塁を許し、さらに守備でもイージーではないが止めたい場面が続いた。
観点は3つ:
- 継投タイミング:スネルの球威・球質が落ち始めた瞬間を、攻撃側が正確に嗅ぎとってカウント進行を有利化。投手交代は「結果」ではなく「兆候」に基づく決断が必要。
- 捕球とブロッキング:暴投は投手責任が前提だが、WSでは捕手のワンバウンド処理・体の入れ方・弾きの方向までが失点期待値を左右する。
- 内外野の一歩目:ゴロ・ライナーの初動(第一歩の角度・スプリットステップのタイミング)が走者の進塁抑止に直結。細部の1プレーが「連鎖」を断てるかを決める。
第6戦でドジャースがまず断ち切るべきは、この“細部の誤差”である。
ベッツの不振とロバーツの信頼――「中心は中心であり続ける」
ムーキー・ベッツはWSで23打数3安打、第5戦も4の0(2三振)。守備での不安定な送球も見られた。一方でロバーツ監督は起用継続を明言し、焦燥をリセットさせるメッセージを送った。
「身体面の問題はない。少し焦りが見えるが、彼は乗り越えられる」――ロバーツ監督
逃げ道を作らない信頼は、シリーズ終盤のロッカールームを締め直す。中軸の「最初の1本」が、相手先発の球数・配球設計を変え、以降の打席群に波及する。
第6戦:山本由伸は“序盤3イニング”で試合の温度を下げられるか
2試合連続完投の山本は、「勝つだけ」と繰り返す。第3戦で中1日ブルペン入りも影響なしと明言。球種間の球速帯の分離、ゾーン高低の出し入れ、テンポを制御する間合いが強みだ。
対するブルージェイズは、シュナイダーが山本を「予測不能・球威抜群・頭が切れる」と評し、序盤から球数を嵩上げする意図を示唆。
鍵は初回〜3回:ここで無失点(最悪でも最少失点)に抑え、スタンドの熱量を下げ、打線に「1点でひっくり返せる」空気を戻せるか。山本の強みは先手でストライクを取れることと、打者の反応を見て即座に微調整できること。四球で自らカウント不利を作らない投球が、相手の「早打ち+球数稼ぎ」の矛盾を露呈させる。
先発マッチアップの論点(概念比較)
| 項目 | 山本(LAD) | ガウスマン想定(TOR) |
|---|---|---|
| 象徴球種 | フォーク/カッター/精密4シーム | スプリット/4シーム |
| 初回安定度 | ◎(テンポ良く入れる) | ○(球威は一級、球数は嵩み得る) |
| 再戦アジャスト | ◎(観察→即修正) | ○(スプリット見切り勝負) |
| ゴロ誘発 | ◎(低目集約で内野戦術活性) | ▲(フライ増、長打の芽) |
第6戦の勝敗を分ける「3つの分岐点」
- 先制の攻防:第5戦の「3球2点」を二度と起こさない。初球の入り方(高さ/コース/球種バランス)を共有し、捕手と明確に合意形成する。
- 中軸の最初の1本:大谷・ベッツは結果が必要。打球質の改善兆候を「スコア」に変える最短ルートは、初球〜2球目のド真ん中見逃しをなくすことと、ゾーン下の見極め。
- 7回イニング・マネジメント:投手の球質低下のサイン(腕の遅れ/高さバラつき/空振り→ファウル化)を早期検知。継投は1人早くを合言葉に、守備はクリーンを徹底する。
確率の現実と“反発力”――25.9%は低いか、高いか
ポストシーズンの7戦制シリーズで、2勝2敗から第5戦をホームで落とし、第6・7戦をロードで戦うケースの逆転突破率は25.9%。数字だけ見れば4回に1回だが、ドジャースは過去にアウェイ連勝での突破を経験しており、「大舞台での反発力」は組織文化として根付く。
ロバーツ監督は試合後に「フレッシュに臨む。勝つ方法を見つけるだけだ」と繰り返した。これは精神論ではない。細部の精度、カウント先行、最初の1本――勝つために必要な要素は具体的で、再現可能だという意思表示である。
守備・捕手の視点――“1球の価値”を最大化する
第5戦の暴投連鎖は、投手責任に収れんされがちだが、捕手側の構えの情報量(外し幅・ミットターゲットの静止時間)、ブロッキングの体の入り、弾いた後の方向制御まで含めて「点」に直結する。第6戦は山本の低目集約が増えるため、捕手はワンバウンド処理の頻度が上がる。“前で止める/正面に弾く”の徹底は、進塁抑止=得点期待値の抑制に直結する。内野は一歩目の角度をより前傾に、外野はライナー対応のスプリットステップのタイミングを早めに設計したい。
攻撃の再設計――「ボール1つ下」の見極めと、球数の作り方
イェサベージに対しては、4シームとスプリットのトンネル一致が崩し切れなかった。第6戦に向けては、ガウスマン想定のスプリットに対し、ボール1つ下の見極めをチーム基準に上げる必要がある。
また、初球見逃し→追い込まれるパターンを減らすため、ゾーン内甘めの早い球は躊躇なく叩く。その上で、ファウルで粘るのではなく、スイングの強度を保ったまま球数を作る(=コンタクトを弱くしない)ことが、長打の芽と与四球の両方を引き寄せる。
結論:必要なのは“完璧”ではなく“反発”――第6戦のキーワード
- Shut down the 1st:初回ゼロ。
- First knock:大谷・ベッツの最初の1本。
- Clean&Quick:7回の継投と守備をクリーンかつ早めに。
完璧な試合は要らない。負の連鎖を断つ最初の1プレーこそが、シリーズの流れを反転させる。山本由伸は「勝つだけ」と語った。今のドジャースに求められるのは、その言葉どおりのシンプルさだ。
第6戦、日本時間11月1日。ロジャースセンターで、扉をこじ開けるための90〜120球が投じられる。
参考・出典(一次情報・整合確認済)
- MLB.com/MLB公式日本語サイト(第5戦技術分析・第6戦見どころ)
- TBS NEWS DIG/日テレNEWS NNN(7回の失点経緯・監督/選手コメント・山本の状態)
- 中日スポーツ(イェサベージの記録/逆転確率25.9%データ)
- IBC岩手放送・日刊スポーツ(大谷の各打席描写・球速/打球速度)


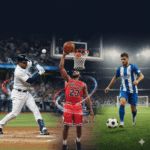
コメント