2025年の「本屋大賞」は、阿部暁子さんの小説『カフネ』(講談社)が見事に大賞を受賞しました。
全国の書店員が「自分の店で売りたい本」として選んだこの作品は、家族の死をきっかけに始まる繊細な人間関係と、食事を通して紡がれる再生の物語として、多くの共感を呼んでいます。
本記事では、『カフネ』がなぜ書店員たちの心を掴んだのか、そして読者が今この物語に惹かれる理由を深掘りしながら、翻訳小説部門や発掘部門など2025年本屋大賞の全体像も紹介していきます。
- 2025年本屋大賞の全受賞作と選考背景
- 大賞作『カフネ』の魅力と社会的共感の理由
- 翻訳・発掘部門など多様な読書トレンドの広がり
本屋大賞2025の受賞作『カフネ』が読者の心を動かす理由とは?
2025年の本屋大賞を受賞した『カフネ』は、書店員の共感を集めた作品として全国で話題を集めています。
本作は、家族の死とその後の再生をテーマにしながら、食とケアが交差する関係性を深く描いています。
なぜこの物語が今、ここまでの反響を呼んでいるのか、その背景と読者の感情に響く理由を探ります。
「食」を通じて描かれる繊細な人間関係
『カフネ』の物語は、弟を亡くした姉・薫子と、弟の元恋人・せつなが「食」を通して関係性を築いていく過程を描いています。
せつなが振る舞う温かい料理が、心を閉ざしていた薫子の気持ちを徐々に解きほぐしていく描写は、読者にも深い共感と感動を与えます。
「食べる」という行為が、単なる栄養摂取ではなく、心のケアとして機能しているという視点は、現代社会における食事の価値を再認識させられる部分です。
“家事代行”を舞台に再生する二人の女性の物語
本作のもう一つの大きな特徴は、せつなが働く家事代行サービス「カフネ」という舞台設定です。
他人の生活に入り込む「家事代行」という仕事を通じて、彼女たちは多様な人々と接し、自分自身の傷を癒していきます。
その姿は、現代の人間関係の希薄さを浮き彫りにする一方で、人との接点の大切さを改めて思い出させてくれます。
“共感”が広げた受賞の輪と地元・岩手の盛り上がり
著者の阿部暁子さんは岩手県花巻市出身で、地元の書店も『カフネ』の受賞に大いに湧いています。
受賞翌日には盛岡市の「さわや書店」などで特設コーナーが設けられ、地元ファンが続々と購入する様子が報じられました。
地域と物語の繋がりが読者の心をさらに近づけ、“この本を売りたい”という書店員の強い想いが、全国的な広がりを生んだのです。
本屋大賞の投票システムとは?選考方法を徹底解説
「本屋大賞」は、全国の書店員が“自分の店で売りたい本”を投票で選ぶ賞として知られています。
その選考過程には、一次・二次の厳格な投票手順が設けられており、読者と本をつなぐ“プロの眼”が反映された独自性のある賞です。
本章では、どのようなプロセスで受賞作が選ばれるのかを詳しく解説していきます。
一次・二次投票に参加した全国の書店員たち
2025年本屋大賞では、一次投票に全国の488書店から652人の書店員が参加しました。
この投票では、書店員が過去1年間で「面白い」「売りたい」と感じた本を自ら選び、推薦理由と共に投票する形式です。
一次投票で選ばれた上位10作品が「ノミネート作」となり、そこからさらに336書店・441人の書店員による二次投票が行われ、最終順位が決定されます。
「売りたい本」を選ぶ本屋大賞のユニークな意義
本屋大賞の最大の特長は、“売れる本”ではなく“売りたい本”を基準にしている点です。
商業的成功よりも、書店員自身の「これは伝えたい!」という熱意が大切にされているため、毎年読者に新たな発見をもたらす作品が選ばれます。
これは単なる文学賞とは異なり、書店と読者との架け橋としての役割も担っているのです。
大賞発表の場としての“明治記念館”とその重み
2025年の本屋大賞発表会は、東京・明治記念館で開催されました。
この場には多数の書店関係者やメディアも集まり、書店員たちの思いが全国へと発信される重要な瞬間となります。
“読書文化の未来”を背負う賞として、今や大きな社会的意義を持つ存在といえるでしょう。
『カフネ』以外のノミネート作にも注目!上位作品の魅力を紹介
2025年の本屋大賞では、『カフネ』だけでなく、多彩なジャンルの作品がノミネートされ、書店員や読者の注目を集めました。
2位から10位にランクインした作品も、それぞれに深いテーマや強い物語性を持ち、“今読みたい物語”として高い評価を受けています。
ここでは、ランキング上位作品の概要とその魅力についてご紹介します。
2位『アルプス席の母』、3位『小説』ほか、注目の10作品
- 2位『アルプス席の母』(早見和真/小学館):家族とスポーツをテーマにした感動作。東京オリンピックに絡んだ母と息子の絆を描く。
- 3位『小説』(野崎まど/講談社):タイトルそのものが挑戦的なメタフィクション。小説という概念を問い直す意欲作。
- 4位『禁忌の子』(山口未桜/東京創元社):ファンタジーと社会問題を織り交ぜた注目の新人作家による力作。
- 5位『人魚が逃げた』(青山美智子/PHP研究所):現代社会に生きる女性たちの心をすくう短編連作。
どの作品も書店員が「売りたい」と思った理由が読み取れる内容で、物語の力とタイムリーなテーマ性が光っています。
講談社・小学館・東京創元社など出版社別の動向
今回の本屋大賞では、講談社が3作(1位・3位・9位)をランクインさせる強さを見せました。
小学館は2位・7位・8位に入り、注目作を数多く送り出しています。
東京創元社、筑摩書房、PHP研究所など中堅・個性派出版社の存在感も目立ち、出版界全体の多様性と活気が表れた結果となりました。
“大賞以外”の作品にもチャンスがある本屋大賞の魅力
本屋大賞のもう一つの魅力は、ノミネート作すべてに注目が集まる構造にあります。
過去にも大賞を逃した作品が後に映像化されたりベストセラーになるなど、「ノミネート=良作の証明」としての信頼があります。
大賞作だけでなく、ランキング上位全作品をチェックすることが、読書の幅を広げる最良の方法と言えるでしょう。
翻訳小説部門の受賞作『フォース・ウィング』と話題の韓国文学
2025年本屋大賞では、翻訳小説部門にも多くの注目が集まりました。
その中で1位を獲得したのが、レベッカ・ヤロス著『フォース・ウィング―第四騎竜団の戦姫―』です。
また、2位には同点で韓国文学の傑作『別れを告げない』と『白薔薇殺人事件』がランクインし、海外文学への関心の高まりが見て取れます。
ノーベル賞作家ハン・ガンの『別れを告げない』も同率2位
韓国の作家・ハン・ガンが2024年にノーベル文学賞を受賞し、その注目作『別れを告げない』が日本でも高く評価されました。
この作品は、済州島四・三事件を背景に女性たちの再生を描いた物語で、日本の読者にも深い共感を呼んでいます。
文学性の高さと時代を超えるテーマにより、翻訳文学の可能性を広げる存在としても注目を集めています。
韓国文学の高まりと日本読者との共鳴
近年、日本では韓国文学の存在感が急上昇しています。
『アーモンド』や『不便なコンビニ』などのヒットに続き、感情と社会的背景を織り交ぜた作品が次々と話題になっています。
翻訳者による丁寧な言葉選びも相まって、韓国文学は今や“世界文学”の一角として日本の読書シーンに定着しつつあります。
ファンタジーと社会批評を融合した『フォース・ウィング』の魅力
翻訳部門で第1位に輝いた『フォース・ウィング―第四騎竜団の戦姫―』は、骨太な世界観と女性の成長を描いたファンタジー作品です。
戦争と支配のなかで自立と絆を築く物語は、ジャンルを超えて多くの読者の支持を集めました。
本屋大賞という舞台で紹介されたことで、翻訳作品の魅力に気づいた新たな読者層も増えているようです。
発掘部門では『ないもの、あります』が選出!ジャンルを超えた再評価
本屋大賞2025では、過去作を対象とした「発掘部門」でも注目の一冊が選ばれました。
クラフト・エヴィング商會による『ないもの、あります』が、実行委員会の共感を得て「超発掘本」に認定されました。
ユーモアと知的刺激が融合したこの一冊は、時代やジャンルを問わず再評価される価値があることを証明しています。
時代を超えるユニークな作品への書店員の推薦
発掘部門では、2023年11月30日以前に刊行された本の中から、書店員が「今こそ読まれるべき」と思う1冊をエントリーし推薦します。
今年選ばれた『ないもの、あります』は、存在しない商品を紹介するという“矛盾”を楽しむカタログ形式の書籍です。
読者の想像力をくすぐり、読むたびに発見があるという点が高く評価されました。
“くすぐられたい”読者に贈る、新たな読書体験
推薦コメントでは、「心を揺さぶられるよりもくすぐられたい読者にぴったり」と表現されており、知的ユーモアを求める読者層への強い訴求力がうかがえます。
この本は、ことわざ辞典のような語感の商品名と、不思議なイラストが合わさることで、現実と空想の境界を曖昧にします。
まさに「読むだけで脳がほぐれる」ような体験ができる一冊であり、読書の楽しさを再発見させてくれる存在です。
「発掘部門」が読者にもたらすもう一つの魅力
本屋大賞の発掘部門は、新刊の話題作だけでなく、過去の名作にも光を当てる貴重な機会です。
読者に“読み逃していた一冊”との出会いを提供するこの部門の存在は、読書文化を豊かにする仕組みの一つといえるでしょう。
時を経てなお輝く作品たちの価値を、今一度味わってみてはいかがでしょうか。
本屋大賞2025をきっかけに読みたい!読書好きのためのおすすめ活用術
「本屋大賞2025」の発表をきっかけに、読書をより楽しく、充実させるための工夫にも注目が集まっています。
受賞作やノミネート作を軸に年間の読書計画を立てたり、書店フェアを活用して新たな本と出会うのも良い方法です。
この章では、本屋大賞を“読む力”へと変える活用術をご紹介します。
特設コーナーや書店フェアを上手に活用する方法
多くの書店では、本屋大賞発表後に「本屋大賞フェア」や特設コーナーが設けられています。
店頭では作品ごとの紹介POPや書店員による手書きコメントなど、ネットでは得られない“本との出会い”が広がっています。
こうしたスペースを訪れることで、思いがけない良書との出会いや読書の幅が広がることが多く、初心者からベテラン読者までおすすめの方法です。
ノミネートリストを使って1年間の読書計画を立てよう
本屋大賞のノミネート作品は、年間を通して読み応えのあるタイトルが揃っているため、読書計画のベースにぴったりです。
10作品のリストを月ごとに振り分けて読むだけで、テーマもジャンルも多彩な読書体験が可能になります。
また、翻訳部門や発掘部門の作品も組み込むことで、海外文学や過去の名作への関心も広がるでしょう。
読書記録アプリやSNSで“読書仲間”を作る
読んだ本を記録するツールとして、読書メーターやブクログなどのアプリを活用するのもおすすめです。
感想や評価を共有することで、自分の読書スタイルを客観的に振り返ることができます。
さらに、SNSで「#本屋大賞2025」タグを使って感想を投稿することで、同じ本を読んでいる仲間とのつながりも生まれるでしょう。
本屋大賞2025と『カフネ』をめぐる話題とその意義のまとめ
本屋大賞2025は、書店員の「本当に売りたい本」を読者に届けるという原点を貫きながら、多くの注目作を生み出しました。
大賞に輝いた『カフネ』は、現代の人間関係やケアのあり方を問い直す作品として、大きな意味を持っています。
ここでは、本屋大賞という存在が果たす意義、そして2025年のトピックを総括していきます。
読者と書店員をつなぐ“本屋大賞”の存在価値
本屋大賞は、書店員と読者が「面白い本」を共有する場として年々影響力を増しています。
商業的なベストセラーとは異なり、読者の心に長く残る“魂のある本”が選ばれるという点に、多くの読書好きが魅力を感じています。
今後もこの賞は、読書文化の発展に欠かせない存在であり続けることでしょう。
『カフネ』が今の時代に必要とされた理由とは
『カフネ』が受賞した背景には、「食」や「家事」を通して心の距離を縮める物語が、今の社会の空気と共鳴した点が大きいです。
コロナ禍以降、孤独や喪失を抱える人が増える中で、人とのつながりや心のケアに光を当てるテーマが広く受け入れられたのです。
読者にとって、『カフネ』は“読むセラピー”とも言えるような優しさと再生の物語だったのではないでしょうか。
本屋大賞から広がる“新たな読書の輪”
本屋大賞を通して、ノミネート作や翻訳作品、過去作への関心も高まり、読書の幅がぐっと広がる傾向が見られます。
“大賞”というきっかけを入口に、まだ知らなかった名作と出会うことは、読書の醍醐味そのものです。
2025年の本屋大賞が生んだ読書ムーブメントは、これからも私たちの読書体験をより豊かにしてくれることでしょう。
- 2025年本屋大賞は阿部暁子『カフネ』が受賞
- 「食とケア」を通じた再生の物語が共感を集めた
- 書店員の投票で選ばれる独自の選考方式
- 翻訳部門では韓国文学『別れを告げない』が話題
- 発掘部門では『ないもの、あります』が超発掘本に
- ノミネート作品も読書ガイドとして活用可能
- 本屋大賞フェアを通じて全国の書店が盛り上がり
- 読者と本をつなぐ“売りたい本”の祭典として定着
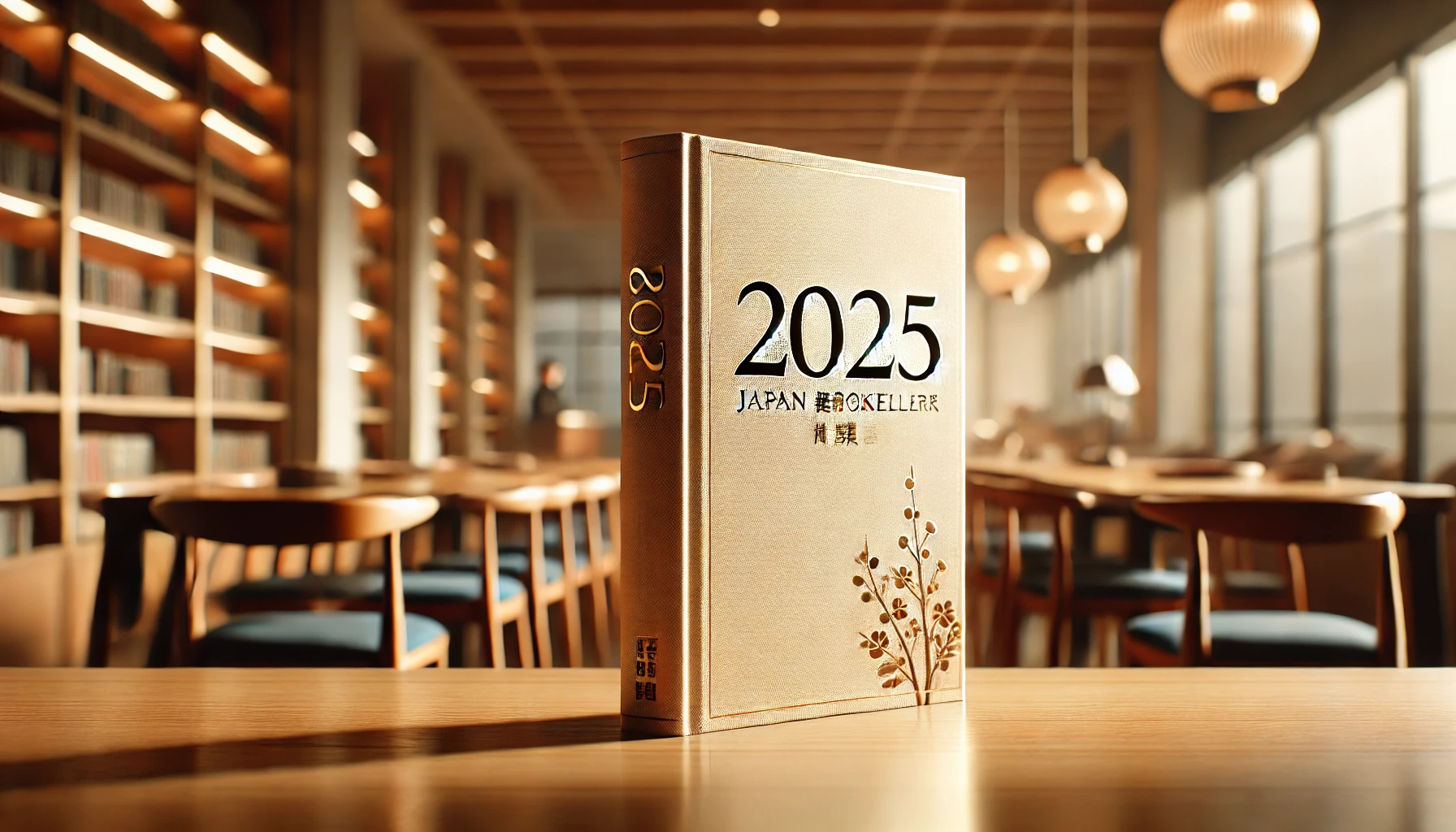


コメント